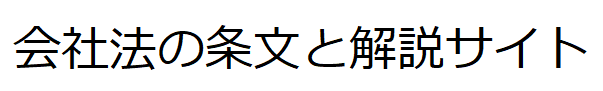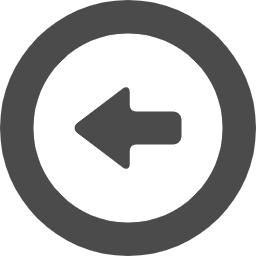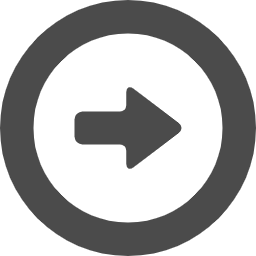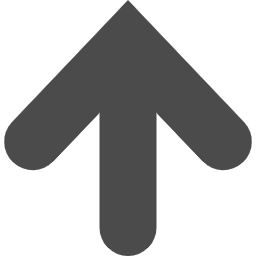会社法308条(議決権の数)を解説します。
会社法308条は議決権の数について規定している条文です。

1.会社法308条の条文
第308条(議決権の数)
1
株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2
前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
2.会社法308条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法308条1項
1
株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
原則は、1株につき1個の議決権です。
ただし、単元株制度を導入すれば、例えば100株を1単元とし、1個の議決権とすることも出来ます(188条)。
カッコ書きの部分は、相互保有株式と言われます。
株式会社Aは株式会社Bの株式全体の1%を保有しているとします。
株式会社Bは株式会社Aの株式全体の25%(1/4)以上を保有しているとします。
この場合、株式会社Aは株式会社Bの株式につき、議決権を行使することは出来ません。
株式会社Bについては、株式会社Aの議決権は行使することが出来ます。
全体の議決権の25%以上を保有している株主は影響力大です。
株式会社Aにとって、株式会社Bは大株主ということですね。
ゆえに、株式会社Aは、株式会社Bの意向に沿った議決権の行使をしがちということで、相互保有株式については、議決権はなしという取扱いになります。
3.会社法308条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法308条2項
2
前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
そのままの意味です。155条の自己株式の取得がされた場合は、全体の議決権から自己株式の数を抜いた株数が議決権行使可能な株式になるので、注意したいところです。
4.司法書士試験の過去問に挑戦
平成5年28問目(会社法)
各株主は1株について1個の議決権を有するとする原則の例外に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
| 肢 | 問い | 正誤 |
| ア | 単元未満株式を有する株主は,その有する単元未満株式については,議決権を有しない。 |
クリック
|
| イ | 会社は異なる種類の株式を発行する場合においては,定款で,剰余金の配当に関して優先的内容を有する種類の株式について,議決権を有しないものとすることができる。 |
クリック
|
|
|
||
| ウ | 会社は,その親会社又は子会社の株式について議決権を行使することができない。 |
クリック
|
| エ | 相互に相手会社の総株主の議決権の4分の1以上の議決権を保有しあっている会社は,それぞれの株主総会における議決権を有しない。 |
クリック
|
| オ | 株主は,自己を取締役に選任する株主総会決議であっても,議決権を行使することができる。 |
クリック
|
 広告・関連記事
広告・関連記事