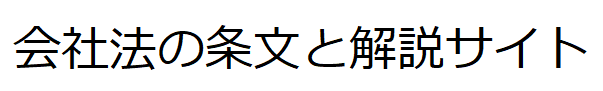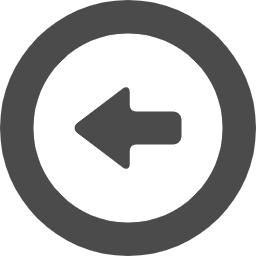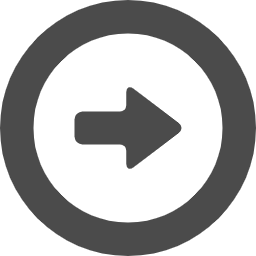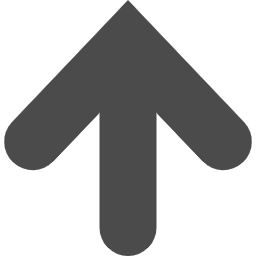会社法188条(単元株式数)を解説します。

1.会社法188条の条文
2.会社法188条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法188条1項
原則は、1株につき1個の議決権です(308条1項)。
単元株式とは例えば10株を1単元とし、1単元につき議決権を1個付与する規定です。
10株を1単元とした場合は、10株未満については、議決権の付与は受けられません。
具体例としては以下です。
株主A 10,000株 → 議決権1,000個
株主B 5,199株 → 議決権519個
株主C 99株 → 議決権9個
3.会社法188条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法188条2項
単元株式数は無制限に決められるわけではありません。法務省令とは会社法施行規則34条のことですが、単元株数は1,000または発行済み株式総数の1/200を超えてはいけません。
コラム
単元株式数に制限を設けているのは、少数株主の保護が目的です。
例えば、10株ずつ保有している株主、1株ずつ保有している株主がそれぞれ多数いたとします。
仮に単元株式数を10株としたらどうなるでしょうか。
1株ずつ保有している株主は、単元株数に満たないので、株主総会でほぼ全ての議案に対して、議決権を行使することが出来なくなります。
会社の株主の状況により異なりますが、場合によっては不公平な決議になることも考えらます。
単元株式数を設けると、このような事が起こり得るので、一定の数を超えないように制限しています。
ただし、少ない株数を保有している株主が多数いて、株主総会の開催にコストがかかる場合は、あえて単元株式数を設けるケースもあります。
この辺りは、会社の要望等をヒアリングして決める部分になりますが、実務上面白い部分でもあります。
以下、具体例です。
株式会社X
・普通株式 1,000,000株
株式会社Xは単元株数をMAX1,000株まで定められます。
1,001株とするのは単元株数が法定の1,000株を超えることになるのでダメです。
続いて、次の具体例です。
株式会社X
・普通株式 100,000株
この場合は、単元株式は500株までとすることが出来ます。
ギリギリ、発行済み株式総数の1/200です。
単元株式を501株とするのは1/200を超えてしまうので出来ません。
4.会社法188条3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法188条3項
種類株式発行会社であれば、それぞれの種類の株式に単元株式数を定めることが出来ます。
例えば、普通株式にのみ単元株式数を100株と、A種優先株式には単元株式数を定めない、ということも可能です。
5.司法書士試験の過去問に挑戦
平成28年29問目(会社法)
単元株制度に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,正しいものはどれか。 なお,種類株式発行会社である場合は,考慮しないものとする。また,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答すること。
| 肢 | 問い | 正誤 |
| ア | 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するには,株主総会の決議によらなければならない。 |
クリック
|
| イ | 単元未満株式の買取りの請求に応じて行う株式会社の当該単元未満株式の買取りにより株主に対して交付する金銭の額は,当該買取りがその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 |
クリック
|
|
|
||
| ウ | 単元未満株式のみを有する株主に対しては,株主総会の招集の通知を発する必要がない。 |
クリック
|
| エ | 株式会社は,単元未満株主が単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができる。 |
クリック
|
| オ | 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を単元未満株主に売り渡すことを請求することができる旨の定款の定めがない場合には,単元未満株主は,株式会社に対して,当該請求をすることができない。 |
クリック
|
 広告・関連記事
広告・関連記事